2024年現在ペットを飼っている人の割合は28.6%、犬と猫合わせて1594万頭が飼育されている。そんなわが子同然のペットの将来を気遣い、ペットに財産を譲りたいと思う人もいるはず。そんな方たちのために、「自分がいなくなっても愛するペットが路頭に迷わない方法」をご紹介します。
まず、「ペットに財産を譲る」と遺言書に書かれていた場合、これはそのままでは無効 になります。
なぜなら、日本の法律ではペットは「財産(物)」と扱われ、人のように財産を相続する権利がない ためです(民法第899条など)。
では、どうすればペットのために財産を残せるのか?
次のような方法を使えば、ペットのために財産を活用することが可能です。
1. 信頼できる人に財産を遺贈し、「ペットの世話をすること」を条件にする(負担付遺贈)
👉 例:
「A(友人)に500万円を遺贈する。ただし、この財産はペット(〇〇)の飼育費用として使用し、最後まで世話をすることを条件とする。」
ポイント:
✅ ペットの世話を条件 に財産を渡せる
✅ 受け取る人(A)が世話を放棄すると、他の相続人から「遺贈の取り消し」を求められる可能性あり
2. 遺言執行者を指定し、ペットの世話を監督してもらう
👉 例:
「Aに500万円を遺贈する。ただし、B(第三者)を遺言執行者とし、Aが適切にペットを世話しているかを確認するものとする。」
ポイント:
✅ 遺言執行者がいれば、ペットの世話が適切に行われているかチェックできる
✅ 使い込みのリスクを減らせる
3. ペット信託を活用する(より確実な方法)
ペットの世話に使うお金を 信託 し、信託管理人(ペットの世話をする人)と受託者(財産を管理する人)を分ける 方法。
例:
「500万円を信託財産とし、受託者(C)が管理し、飼育者(A)に必要な費用を定期的に支払う」
ポイント:
✅ 財産の使い込みを防げる
✅ Aがペットを適切に世話しない場合、交代できる
まとめ
❌ ペットに直接財産を渡すことはできない(無効)
✅ ペットの世話をする人に財産を渡し、条件を付ける(負担付遺贈)
✅ 遺言執行者を指定し、管理を徹底する
✅ 信託を活用し、より確実な仕組みにする
ペットのための遺言を考えるなら、行政書士や弁護士に相談して、適切な方法を選ぶのが安心ですね。
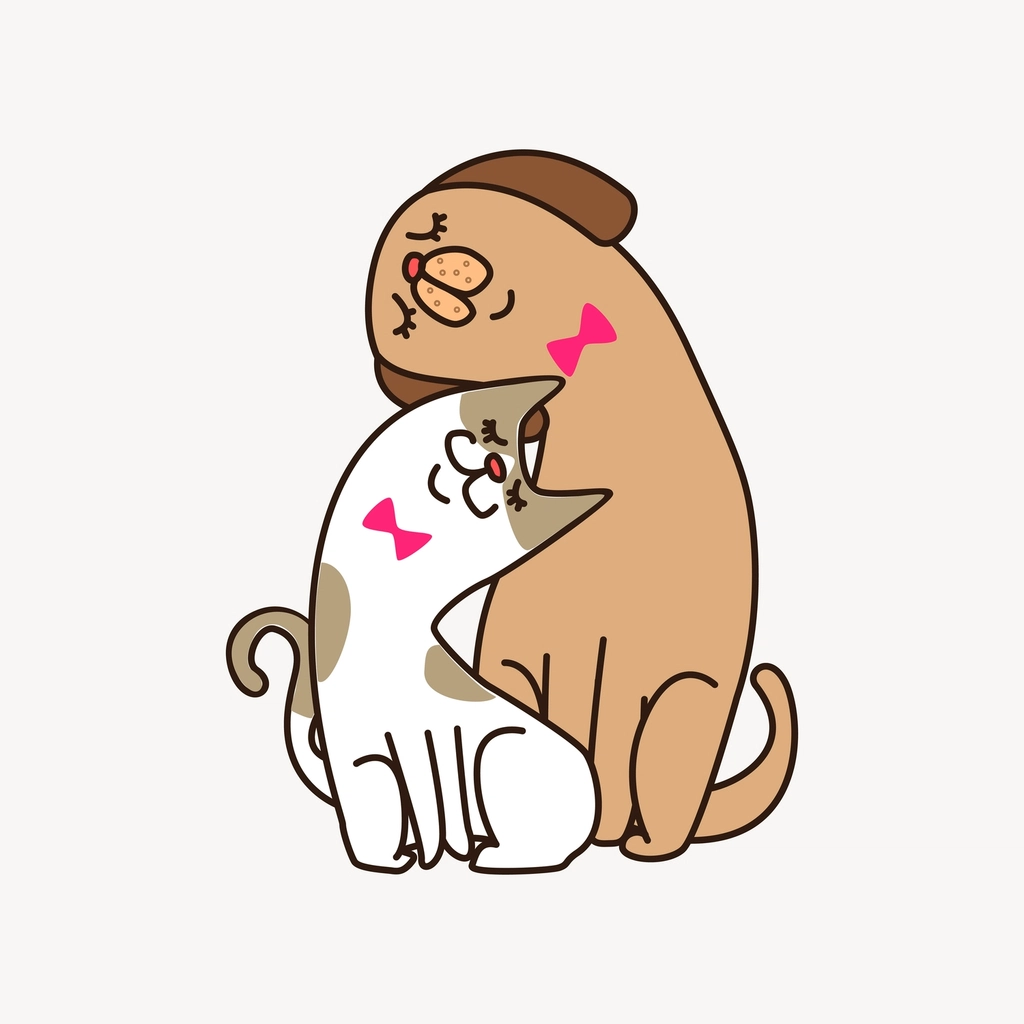

コメントを残す