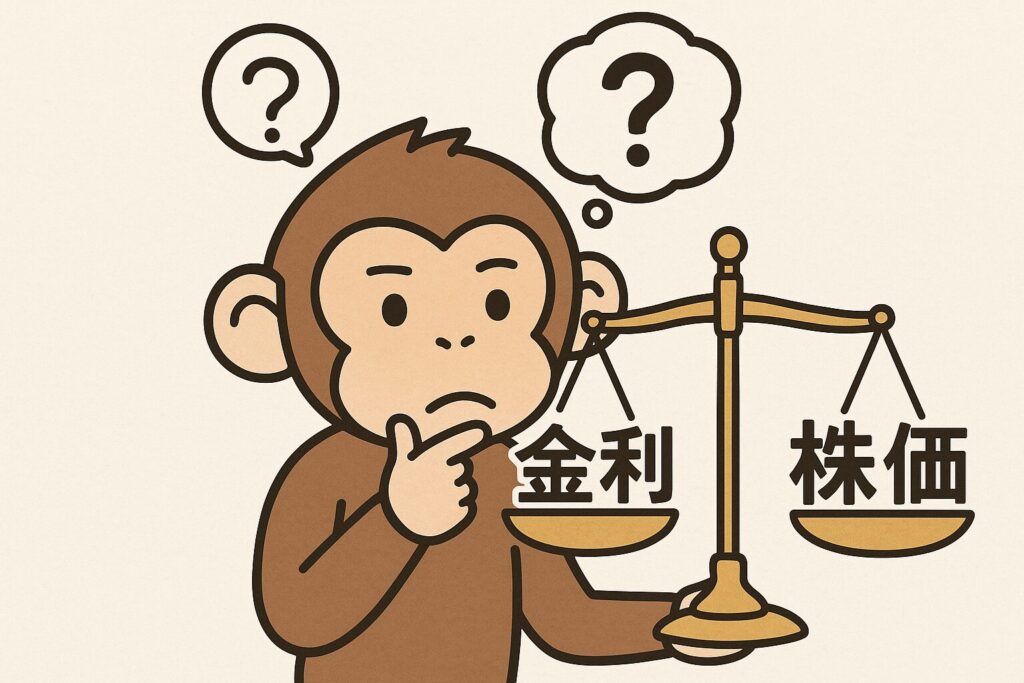
ニュースで「金利が上がると株価が下がる」と耳にしたことはありませんか?
一見別の話のように思える金利と株価ですが、実は経済の中で深く結びついています。
この記事では、
を、初心者の方にもわかりやすく解説します。
はじめに|「金利が上がる=株価が下がる」と言われる理由
金利とは、お金を借りるときの“利息”のことです。
中央銀行(日銀やFRBなど)が政策金利を上げると、企業や個人が資金を借りるコストも上昇します。
結果として企業の利益が圧迫され、株価が下がりやすくなるのです。
💡 ただし、金利上昇は「景気が強い証拠」でもあります。
必ずしも悪いニュースとは限らない点も覚えておきましょう。
金利上昇で株価が下がりやすいメカニズム
① 企業の借入コスト上昇
金利が上がると、企業の借入コストが増えます。
借金が多い企業ほど影響が大きく、利益率の低下につながりやすくなります。
② 安全資産の魅力が高まる
国債の利回りが上がると、安全に運用できる資産の利回りが高くなります。
その結果、投資家は株式を売って債券などの安全資産に資金を移す傾向が強まります。
③ 将来利益の「現在価値」が下がる
株価は、将来得られる利益を「現在価値」に割り引いて算出されます。
金利が上がると割引率も上がり、同じ将来利益でも現在の評価額が低くなります。
このため、特にハイテク株やグロース株は影響を受けやすくなります。
金利上昇に強い業種・弱い業種
金利上昇に強い業種
- 銀行・保険業(利ざや拡大)
- エネルギー・素材産業(価格転嫁がしやすい)
- 生活必需品・インフラ関連(景気に左右されにくい)
金利上昇に弱い業種
- ハイテク・グロース株(将来利益重視型)
- 不動産・建設業(資金調達コストの上昇)
- 高配当だが負債の多い業種(利払い負担増)
📊 ポイント:
業種ごとの特徴を理解し、ポートフォリオを分散することで金利変動リスクを軽減できます。
NISA・長期投資家が慌てないための基本戦略
① 積立で時間分散
毎月コツコツと同額を積み立てる「ドルコスト平均法」は、高値掴みを防ぎ、購入価格を平準化します。
短期的な値動きに惑わされず、長期的な複利効果を重視しましょう。
② 資産分散でリスクを平準化
株式だけでなく、債券・現金・不動産(REIT)など、値動きの異なる資産を組み合わせると、
金利上昇時にも全体のリスクを抑えられます。
③ リバランスで感情を排除
一定期間ごとに資産配分を見直し、増えすぎた資産を売り、減った資産を買い戻す「リバランス」を行いましょう。
この仕組みを取り入れると、感情に流されず安定的な投資ができます。
👉 関連ページ: NISAの基礎と活用法はこちら
金利・景気・インフレの関係をどう読む?
金利上昇は、しばしば「インフレ抑制」や「景気の過熱を防ぐ」目的で行われます。
景気が強ければ金利が上がっても企業業績は支えられることもあります。
つまり、「金利」だけでなく「景気」と「物価」の動きを合わせて見ることが重要です。
📈 参考: 経済ニュースの読み方を学ぶ
よくある質問(Q&A)
Q1. 金利が上がると必ず株価は下がりますか?
→ いいえ。金利上昇が「景気の回復」を示すものであれば、株価が下がらない場合もあります。
Q2. 金利上昇局面でNISAを続けてもいいですか?
→ はい。短期的な変動よりも長期の積立を優先しましょう。焦って売却せず、非課税の恩恵を活かすことが大切です。
Q3. 債券や預金に移したほうがいい?
→ 資産の一部を安全資産に移すのは合理的ですが、長期投資の軸は維持しましょう。
リスク許容度に合わせた配分(株・債券・現金)を守るのが基本です。
まとめ|長期・分散・積立でぶれない投資を
- 金利が上がると株価が下がるのは、資金コスト・安全資産の利回り・心理要因など複数の要素が関係。
- ただし、景気が強ければ必ずしも株価が下がるとは限らない。
- **長期投資は「積立・分散・リバランス」**が最強の防御策です。
💡 関連記事:投資初心者が知っておくべき基礎知識
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定銘柄や投資判断を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

コメントを残す